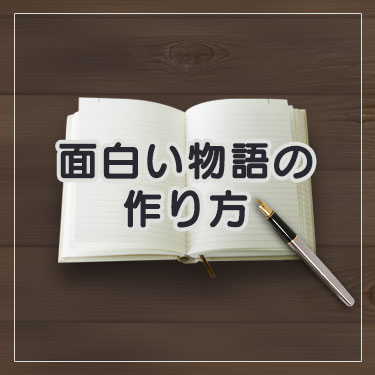ストーリーの前提条件
今まで物語を作るための基本条件を確認してきました。
今回は長編ストーリーの作り方を考えていきたいと思います。
その前にまず、決めなければいけないことがあります。
それはストーリーの前提条件を設定することです。
簡単な例を挙げてみます。
「落ち武者が自分の息子を探す話 」と前提します。
では、この作品の背景を考えましょう。
六何の原則でまとめてみよう。
- いつ – 戦国時代
- どこで – 関ヶ原
- 誰が – 明智光秀の軍団
- 何を – 落ち武者狩りと戦う
- どのように – ボロボロな刀を持って逃げながら
- なぜ – 生き延びて家族に会うために
前提条件はできるだけ簡潔に読者に説明をしましょう。
ぱっと見れば「なに?簡単なんじゃないの?」と思いますが
この前提をきちんとできないとこんな感じの物語の書くことになるでしょう。
ダメな例
ダメな例を書くと
「帝国歴1825年。皇帝イグリナスとその大敵者カナトゥスの戦争が終わってから100年が経っていないある日、大将軍オクトニシウスと彼の手下アルカチオンは暗い部屋で………」
どこでたくさん見た小説の始まりだと思いませんか?
前提が貧弱な物語は大概にこう始まります。
「見知らぬ〇〇だ」
「〇〇歴xxxx年」
「〇〇戦争」
「私の名前は〇〇。普通の○○生だ」
こちらは絶対書いてはいけない物語の始まりの一例です。
読者はそのミームを面白く思うかもしれません、しかし自分がクリエイターを目指しているのであればこのミームを笑う事は出来ないでしょう。
なぜなら自分もそういう風に物語を考える可能性も高い話だからです。
それでは、こんな文章を作り出す理由は何でしょうか?
それが先から言っていた作品の前提条件をきちんと決めていないからです。
帝国歴1825年?皇帝イグリナス?大敵者カナトゥス?
読者からすれば「誰だよ~」って突っ込まれるはずです。
一番重要なのは物語の序盤
不要な情報まみれの作品ははっきり言いますが「面白さ」がない。
我々は「面白さ」を求め作品を見始めるわけで何かしらの「情報」を見たいわけではないのです。
だから何かのストーリーを書く時には物語の序盤1、2話に不要な情報は削ることを意識しなければいけません。
ここまで「前提条件」の大事さを力説すると読者の皆さんもきちんと前提条件を考えていると思って話を進めます。
自己満足ではない、商品として作品をを書く時は、プロローグと第1話にすべてを注ぐべきだと考えます。
それは一話で消費者の興味を引くことができなければ続けて作品を消費てもらえないからす。
それでは、その 六何の原則 を利用してエピソードを作ってみましょう。
六何の原則 を利用したエピソードの作り方
「落ち武者が自分の息子を探す話 」
このテーマでストーリーを作って行きたいと思います。
- いつ – 戦国時代
- どこで – 関ヶ原
- 誰が – 明智光秀の軍団
- 何を – 落ち武者狩りと戦う
- どのように – ボロボロな刀を持って逃げながら
- なぜ – 生き延びて家族に会うために
作家はどうやって面白い第1話を作り出すでしょうか?
これはものすごく悩む問題です。
まず主人公は1話で落ち武者になっていなければなりません。
そうしてそこから話が展開されます。
では、先に設定した前提条件を思い出して主人公の話を考えてみよう。
「落ち武者になって国にある家族に戻る冒険」
「落ち武者なってそのまま身を隠そうとしていたが主の息子の影武者が自分の息子になっていた」
「息子が落ち武者狩りにになっていて侍を恨んでいた」
などなど……
前提条件をきちんと設定していれば、その条件を通じて様々な話を作り出すことができるでしょう。
作家はその中から最もインパクトがあると思われる内容を選へば良いのです。
それでも第1話のインパクトを与えることは実力と経験、才能と運が必要かと思います。
1話を書くのはとても難しいこと。
それでも悩み続けながら書き続けると「これだっ!!」という答えが出るでしょう。
筆者は「落ち武者なってそのまま身を隠そうとしていたが主の息子の影武者が自分の息子になっていた」という1話を書こうと思います。
ここからまた面倒でありますがやるべき過程が生じます。
原因・過程・結果を繰り返す
それではストーリーの原因と結果を考えてみよう。
原因「落ち武者狩りで故郷の人がいて、主が自分の息子を主の息子の影武者として使っていて危ない状況」
過程「主人公怒り狂う」
結果「主人公は息子を奪い返すことに決心」
主人公は息子を奪い返す決心をしました。
そうしたら次は?
原因「落ち武者狩りから逃げようとする」
過程「友人の助けで故郷に向かうがケガを負う」
結果「山奥の民家に休息」
そうしたら次は?
原因「ケガの身では息子を奪い返すのは難しいと考える」
過程「民家の人に自分の話をする」
結果「民家の人は廃れた忍者の一族だった」
そうしたら次は?
原因「忍者の一族は主に裏切られて廃れていた」
過程「復讐の手伝いとして主人公と共にする」
結果「一緒に故郷に向かう」
こういう風に
原因と結果をつなげ話を続けさせます。
このように話が展開される理由は
「原因、過程、結果」を通じて新しい情報を与えているからです。
先に述べたように、物語には不要な情報はいりません。
それは別の表現に切り替えると作品が進行する過程というのは結末に至らせるための必須情報を一つずつ読者たちに提示するという事です。
つまり、作家は不要な情報を切り落とし、必須情報を一つずつ読者に説明することをするということです。
しかしここで注意すべき事は
話を展開するにあたって「原因、過程、結果」にふさわしい内容を展開しなければなりません。
簡単に説明すれば、「辻褄を合わす」「蓋然性(がいぜんせい)」を考えましょうという事。
復讐、息子を取り戻すために故郷に帰ろうとする主人公が突然きれいなくノ一に出会い恋に落ちてしまう話に展開すると話の辻褄があわないという事です。
シンプルではありますが、簡単に忘れる要素の一つでもあります。
まとめ
「原因、過程、結果」というストーリーの必須要素を作ってみました。
そして作家がすることとは「不要な情報を削り落とし、結末に至らせるための必須情報を説明すること」であることが分かりました。
ここまでくると、この次からは再び最初の記事につながります。
作品を展開するためにはテーマがはっきりするべきという事。
そうしてこそ作品が道をそれず結末までまっすぐ進みます。
そして作品について考え続けましょう。
読んで書いて考えて…
これを繰り返し続けていきましょう。
これが創作の唯一の解決法です。
要約
- ストーリーは「原因、過程、結果」に合わせて調整をする。
- 不要な情報を削り落とし、必ず必要な情報だけを読者に説明する。
- ストーリーの辻褄を合わせて話を進める。